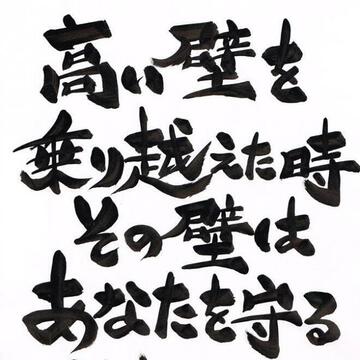8月は中国の景気後退をネタに、世界の株式市場はハゲタカファンドに翻弄されましたが
漸く市場のドタバタ劇も終りを迎えた様です。
今後の株式市場は、米国経済の発展と欧州経済の回復、そして中国経済の踏ん張りにかかっていますが
決して他人事ではなく、日本も世界の経済成長に一役買う立場にあると思います。
今こそ外部要因に振り回されず、国内の景気対策に全力を注げば、株価は後から付いて来る筈です。
また東京市場はアベノミクスで需給が先行し、一時日経平均2万円時代を迎えましたが
経済政策の根幹が金融緩和と公共投資に偏っている現状を
海外の投資家は憂慮しているのではないかと考えています。
安保法改正で不支持率が支持率を大きく上回った安倍内閣に残された最後のカードは
世界が認める景気対策しかない様な気がします。
ところで日米欧の景気は回復基調にあるとしても
中国の景気後退はどの程度深刻なのか?また何時まで続くのかなど
中国経済の実態について少し検証してみたいと思います。
◇高度成長が何時までも続く訳がない
中国のGDP推移①(1980年~2015年4月)
http://ecodb.net/country/CN/imf_gdp.html
中国のGDP推移②(1980年~2014年4月国民一人当たり)
http://ecodb.net/country/CN/imf_gdp2.html
日本のGDP推移①(1980年~2015年)
http://ecodb.net/country/JP/imf_gdp.html
日本のGDP推移②(1960年~2012年、国土交通省資料15Pをご覧下さい)
http://www.mlit.go.jp/common/001020274.pdf
世界各国の名目GDP構成比(総務省統計局資料第3章をご覧下さい)
http://www.stat.go.jp/data/sekai/0116.htm
日本の場合1960年以降、名目GDP(円ベース)は約30倍、1人当たりでは約20倍。
これに対し中国は、1980年以降2015年4月まで名目GDP(元ベース)は150倍
1人当たりでは107倍の伸びを達成しています。
また日本では、1960年から伸び続けたGDPは37年後(1997年)にピークを迎えていますが
中国の場合も1980年を上昇開始の起点として考えれば35年間伸び続けている訳で
経済成長率が前年比を割ったとしても別に憂慮すべき事態だとは思えません。
勿論1年後、2年後、経済成長率の低下がどんどん加速する様であれば問題ですが
ゆっくりとした減速は止むを得ないと考えています。
因みに2020年の成長率は約5%が妥当という予想が多いのも事実で、7%を割ったからといって
世界経済が終わったかの様に騒ぎ立てるのは如何なものでしょうか。
◇中国が「世界の工場」と呼ばれる時代は終わった
中国の1人当たりのGDPはおよそ8000ドルですが、この数値はベトナム2200ドル、インド1800ドル
ミャンマー1300ドルに比べるとかなり高いだけでなく、賃金は年率約10%上昇を続けています。
ですから「世界の工場」としての魅力が無くなれば,、成長率が鈍化するのは当然のことでしょう。
因みに同様の比較では、タイ7500ドル、インドネシア5200ドル(何れも概算)という状況で
近年ベトナムに進出する日本企業が急増している理由が窺えます。
◇先進国の定義(ブランドを持たない国は先進国になれない)
中国が新興国を代表する国であることは間違いありませんが
先進国の仲間入りをするためには、越えなければならないハードルが沢山あると思います。
教科書的な先進国の定義はOECDに加盟してる国だと言われていますが
http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/oecd/html/
その他にも、1人当たりのGDPが10,000ドル以上であるとか、教育水準や平均寿命を指数化した
人間開発指数が高いことなども先進国の条件とされています。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E9%96%93%E9%96%8B%E7%99%BA%E6%8C%87%E6%95%B0
従ってOECD加盟国の中にも、先進国とは言い難い国があることも事実です。
また、現実問題として、世界に通用するブランドを持たない国は先進国とは言えないでしょう。
つまり、ハイテク産業や世界市場を席巻する企業、さらにはオンリーワン企業等の存在が
先進国と呼ばれる条件の一つだと考えられています。
しかしながら中国は教科書的な定義は勿論、ブランド力からも先進国には程遠いと言えます。
しかもブランド力が無ければ構造的に成長率は下がり、内需拡大に賭けるしかありません。
これでは企業の成長は止まり、投資、雇用、消費などの停滞に繋がりかねません。
この点が、コピー商品しか作れない経済大国の致命的な欠陥だと思います。
◇綱紀粛正が経済発展の障害に
習近平国家主席が進める綱紀粛正は、少なくともあと2年程度続くと考えられていますが
その間公共投資が制限されるなど、景気減速に繋がるという見方が広がっています。
そうなると2016年の経済成長もあまり期待出来ないと思います。
◇過剰債務とシャドーバンキングが金融緩和の足枷に
中国政府は景気後退を防ぐため、昨秋から数回に亘り金融緩和に踏み切っています。
しかし2014年末時点の家計・企業・政府合算の債務残高は148.8兆元に達しており
これは名目GDPの233.8%に相当します。
こうした過剰債務の下で金融を緩和を行っても、設備投資が回復する可能性は低く
むしろ企業の債務拡大に追い付けないというの実態だと思われます。
因みに日本では1989年末に、非金融業の債務残高が対GDP比132.2%に達しましたが
中国の場合、2014年末の同比率は156.7%と日本のバブル期を上回っています。
つまり企業の利払い負担が膨らむ一方で、製品の出荷価格の下落が収益を圧迫し
企業が新たな借り入れに慎重にならざるを得ない状況にあることが考えられます。
こうした状況を反映するかの様に、企業の資金需要DI(判断指数)は
金融緩和が開始された2014年秋以降も低下を続けています。
もう一つ、中国には金利を何度下げてもお金が循環しない理由があります。
それは金利の高い不正規金融やシャドーバンキングの規模が大きいことで
市場金利が下がると、銀行は資金を正規市場に流しても儲からないため
金利の高いこれらの運用市場に資金を移動させるからです。
その結果、幾ら金融緩和を行っても、資金を必要とするところには
お金が流れ難いのだと思われます。
◇株価の下落は個人より企業に大きなダメージを与える
上海株式市場の売買高のうち、およそ8割は個人の売買ですが
時価総額に於ける企業保有分は全体の63.4%(2013年)で個人の21.7%を大きく上回っています。
従って、当局が株価維持に形振り構わず取り組むのは、企業業績に対する配慮があるからです。
(関連レポート①)
http://www1a.biglobe.ne.jp/jcbag/seminar104_gaiyo.pdf
◇不動産事情(不動産プチバブル?の崩壊)
中国では地方政府が不動産開発を拡大させて来たため、供給過剰であることは間違いありませんが
現実は、不動産バブルというより、プチバブルと呼ぶ方が個人的にはしっくり来ます。
それというのも、中国に於ける不動産価格や家賃の上昇率は
決してバブルというレベルではなく、例えば2007年から12年までの5年間で
住宅価格の上昇率は30%以下に止まっています。
これに対して84~89年の5年間で、日本の不動産価格は2倍近く上昇しました。(日銀レビュー)
また世界的な金融不安へと発展したサブプライムローンとしばしば比較されますが
中国にはその様な手厚いローン制度が無いため、たとえ住宅価格が大幅に下落しても
資産価値が減少するだけで、連鎖的な金融不安が起こる可能性は無いと考えています。
しかも中期的に不動産需要は高まることが予想されており
少なくとも「中国不動産バブルの崩壊」という表現は的を得ていない様な気がします。
但し、ここでもシャドーバンキングの存在は障害になり得るので
金融緩和効果をより高めるためにも、シャドーバンキングに対する規制強化は必要だと感じます。
(関連レポート②)
http://www.mri.co.jp/opinion/mreview/topics/201502-1.html
◇中国経済の課題
中国は世界の工場としての役割を終えようとしており
今後は先進国の仲間入りを果たす努力(構造改革)が必要だと思います。
そのため習近平・李克強体制の下では、構造改革や技術革新が最優先課題とされており
製造業は加工組立産業から、高度な先端産業(独自ブランドの育成)を目指し
産業構造を製造業偏重型から、消費やサービス産業へ移行させようとしています。
またそうすることによって、製造業の生産性向上で溢れた失業者を吸収することも可能になる訳です。
しかし景気を悪化させずに構造改革を推し進めることは非常に困難です。
現在中国政府は、成長率より構造改革を優先させたいと考えている様ですが
構造改革を疎かにしたまま金融緩和を行えば、過剰設備を抱え構造改革を必要としている企業が
積極的に構造改革に取り組まなくなる恐れがあります。
一方、金融緩和を行わなければ景気は益々後退し社会不安が拡大
その結果政権運営に支障を来たす恐れが生じます。
つまり金融緩和を優先すれば大命題である構造改革が進まない。
逆に構造改革を最優先して金融緩和を後回しにすれば景気の悪化が止まらない。
その上、不動産プチバブルのハードランディングを招くことにもなりかねません。
つまりどちらを優先しても大きなリスクを伴うことから
中国経済の方向感は、暫く見え難い状況が続くのではないかと思われます。
因みに中国の楼継偉財政相は、先般トルコで開かれたG20財務相・中央銀行総裁会議の席上
今後5年は経済構造改革の痛みを伴いながらも、現在と同じ7%成長が続くとの見通しを示しました。
さらに同氏は、高度経済成長期は終わったとした上で
2桁成長時代に積み上がった在庫と過剰生産設備の解消には数年かかると指摘し
「今後5年は構造調整の陣痛期」と位置付けています。
これまで中国は投資主導で経済成長を押し上げて来ましたが
過剰な生産能力(設備)や地方債務の増大など多くの副作用を生んだことから
消費主導型経済への移行を進めようとしていることは明らかです。
またこの先、景気対策として財政支出を増加させる意向も示しましたが
果たして7%前後の経済成長率が続くかどうかは甚だ疑問であり(むしろ無理?)
個人的には、5年後の2020年には5%程度に縮小しているのではないかという見方に賛成です。
しかもさらにその先は、4%→3%→2%と漸減するのが自然の流れではないかと思います。
つまり、仮に来年中国の経済成長率が7%を大きく割り込んだとしても
中国政府としては内心織り込み済みのことであり
少なくとも周囲が大騒ぎするのは筋違いだというのが私の結論です。