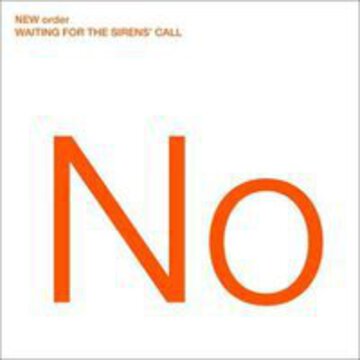#4
http://minkabu.jp/blog/show/100980
私が言及した種類の洗練された金融工学は、マージンと必要資本の計算を困難なものか、もしくは不可能なものにする可能性がある。このような要求を活性化するために、金融工学は規制されなければならなく、新たな商品は登録されなければならなく、それらが使用される前に適切な監督機関によって承認されなければならない。このような規制は、オバマ新政権において高い優先順位であるべきだ。それは一層必要だ。なぜなら、金融工学はしばしば規制を巧みに逃れることを目指すからだ。
CDSを例にとると、その商品は債券やほかの債務がデフォルトする可能性に対して保険をかけることを目的としていて、その価格はデフォルトの可能性について認識されたリスクを示している。このような金融商品は、トプスィー(Topsy:第二次世界大戦で使用された陸軍100式輸送機の連合国コードネーム?)のように成長する。なぜなら、実際の債券を保有したり空売りしたりするよりも少ない資本で済むからである。最終的にそれらは、50兆ドル以上にまで膨れ上がり、それは実際の債券に対して幾層倍にもなり、米国債全体の5倍にもなった。しかし、CDS市場はまったく規制されていないままになっている。保険会社であるAIGは、保険商品としてCDSを売ることで資産を失い、今までのところ1260億ドルの負担を財務省にかけて救済されることになった。CDS市場は、最終的には他の多くの市場で起こったような崩壊からは守られるかもしれないが、この規模の規制されていない市場の純然たる存在は、金融市場全体において増大するリスクの最大の要素であり続ける。
今まで使われてきたリスク管理モデルは再帰性に内在する不確実性を無視してきたので、今後は信用とレバレッジの限界はこれまで許容されてきたものよりも大幅に低くされるだろう。金融機関は全体では、スーパーバブルの間よりも利益を上げるのを難しくし、過度のレバレッジに依存してたいくつかのビジネスモデルは利益が出せなくなるだろう。金融セクターが時価総額ベースで市場全体に占める割合はすでに25%から16%に低下している。この割合は、もとの高い割合にもどることはなさそうであり、より低くく終わりそうである。これは(市場全体では)健全な調整とみなされるかもしれないが、職を失った当人からしてみればそうではないだろう。
ヘッジファンドに関して言えば、それらは現在弾けているバブルにおいて欠くことのできない位置をしめていると認識されるべきだ。ヘッジファンドは元金ベースでおよそ2兆ドルまで成長し、それは時には(レバレッジをかけて)運用資産ベースで10兆ドルかそれ以上を動かしていた。しかし今やバブルは弾け、ヘッジファンド業界は大幅に縮小することになるだろう。私は、彼らの運用する資金量は50%~75%縮小すると推測する。現在の金融危機の間、多くのヘッジファンドマネジャーは、下落相場の間に投資家の資産を守るというヘッジファンドの基本的なルールを忘れた。ヘッジファンドが調達した資金の多くが、”α”を求めた通常は堅実な年金や寄付基金からのものであったのは、不幸なことだ。(α:ベンチマークに対する超過リターン)
一般社会が受けた甚大な損失を考慮して、過度の規制緩和が今度は懲罰的な再規制になる危険がある(締め付け過ぎになる恐れ)。それは不幸なことだろう。なぜなら、規制というものは市場メカニズムよりもずっと不完全である傾向があるからだ。私が提案したように、監督機関は人間であるだけでなく官僚的であり、ロビー活動や汚職の影響を受けやすい。ここで概略を示された改革案が、規制によるオーバーキルを事前に防ぐことを望む。
私の証言が、委員会がこれらの問題点を理解する助けになればと思います。質問があればお願いします。
*****これで終わりです*****
感想。自由主義経済、市場原理主義の時代は終わったのだろう。10月に、グリーンスパン氏は持論の一部について過ちを認めるとともに「過去20年間はユーフォリアだった」と言った。ソロス氏の言う、信用とレバレッジの継続的な膨張、すなわちスーパーバブルがユーフォリアにつながった。そのユーフォリアの間に生み出されたものは、金融帝国アメリカ、住宅バブル、消費大国アメリカ、そこに向けて輸出を行う日本や中国や新興国各国の貿易黒字、製造業の成長、物を作るのに必要な資源の採掘、資源ブーム。これらは全てつながっている。金融関係者以外でも、多くの人が直接的間接的にそれなりの恩恵を受けてきた。今はこれが逆回転している。
金融当局は、マネーサプライだけでなく、信用とレバレッジをコントロールしていくことが求められる。現在は、バブルの逆回転で信用もレバレッジも自ら収縮している。規制も必要だが、厳しくしすぎると経済活動を殺してしまう可能性がある。それと、現状の too interconnected to fail の状況をほぐさないといけない。金融機関や金融商品や企業の債務などが、あまりに相互接続しすぎている。どこかが破綻しても、それが連鎖しないようにつながりを弱める。それは恐らく、ビジネスの効率を落とすのだと思う。
大量生産、大量消費で夢のような高成長が続くような状況はしばらくはこないのだろう。日本の製造業も厳しいと思う。今年来年は、バブル崩壊のダメージで景気も株価もダメだろうけど、その後の景気回復期でも回復は緩やかなものになるのだと思う。ただ、今の大量のドル紙幣印刷の反動で貨幣価値が減耗し物価が上がり、名目経済成長率が高くなる可能性はある。その場合は株価も上がるだろう。(物価との対比ではたいして上がらないと思うが)
- 重要なお知らせ 一覧