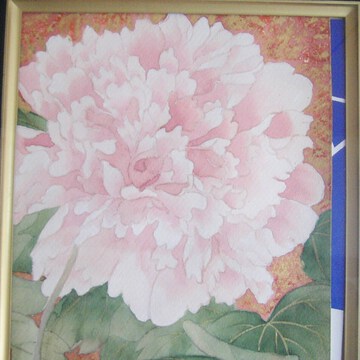昔は、株はギャンブルと思っていても、ギャンブルという人はいませんでした。最近ではギャンブルだという人がほとんどです。
株には、二つの面があります。勝ち負けを争うゲームと、資産を増やす面とです。本来株式投資の目的は、投資によって企業活動を支援し、経済を発展させ国を豊かにし、その果実として値上がり益や配当を受け取り、個人資産を増やしてゆくということでした。これが昔の考え方です。
でも、多くの人は、株がギャンブルであることを知っていました。口には出しませんでしたが、娘は証券マンに嫁がせたくなく、息子は証券会社に勤めさせたくないとの風潮がありました。
ところが、1990年のバブル崩壊以降、それまで個人が中心だった売買主体が機関投資家に変わり、さらに2000年以降は、外国人が占めるようになりました。この間、コンピューターの普及と情報革命によって、情報の大衆化と国際化が進み、つれて売買手数料が大幅に引き下げられ、取引量の増大に繋がりました。
個人投資家も機関投資家に負けない投資環境になった結果、利幅で儲けるより数量でこなす売買方法になり、株式売買がより短期に変わってゆきます。短期運用では相場がどちらに動いても、売り買いとレバレッジで利益をあげることができます。
日経新聞によると、投資家の9割が短期投資家とあります。このように、短期取引が、株式投資の主流を占めるようになった結果、今日では株式市場をゲーム(ギャンブル、ばくち)と見る人が圧倒的に多くなってしまいました。
そうはいっても、さすがにギャンブルとういう言葉には抵抗があるようで、証券会社ではリスクとリターン、個人投資家もゲームに置き換えているようです。
言葉はどうあれ、ギャンブルである限り、儲ける人もいれば損をする人も出ます。もっと端的にいえば、あなたの儲けは、そのゲームに掛けた人の掛け金を受け取ることで生じているのです。当然のことながらゲームに負けた人は、掛け金を失うことになります。
昔の賭場を想像したら、もっとはっきりします。丁半の目の出る確率は五分五分としても、勝った人は負けた人の掛け金を受け取り、負けた人は指をくわえてみているだけです。その間に、胸をさらしでくるんだ美人の姉御が、掛ける人の割合をコントロールしたり、テラ銭をもらったりして、場の維持発展をはかっているのです。
もちろん、政府公認の賭場はありませんから、場所を提供するのはやくざの大親分で、彼らの生計は、賭場をいくつ持つかで決まってきます。大親分は賭場の経営者であって、決して丁半を掛けていた博徒ではありません。
現在の株式市場が、昔の賭場と同じだなんていうつもりはありません。現在の多くの国には株式市場があり、市場が経済の潤滑機能として経済の発展を支えているのです。
証券会社は、以前より優秀な人が集まり、国会議員の中にも市場出身者が多くなってきました。いまや証券マンは、ホワイトカラーの中心を担うまでにステータスも上がってきています。
ただ、最近の証券市場は、ヘッジファンドや、大口の機関投資家にばかり有利になり、個人投資家の利益はますます置き去られているように思われます。
証券税制改革とNISA導入も政府のいいなり、超高速取引システムの導入、最近では銭単位の取引など、個人投資家にとってはほとんどメリットのない市場に変わっています。しかもほとんど事前の予告も議論もないまま、勝手に進められています。
このままでは個人投資家は、ますます市場の片隅に追いやられ、政府公認のギャンブルで憂さを晴らすだけの存在になりかねません。
もう一度投資によって企業活動を支援し、経済を発展させ国を豊かにし、その果実として値上がり益や配当を受け取り、個人資産を増やしてゆくという株式投資本来の目的に沿うように、国も、市場も、証券会社もそして個人も、考え方を変えてゆきたいものです。