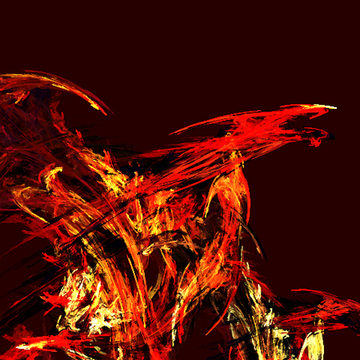ネタ元は、サーチナですが。基本的に普段ここは親中なんですがね。
http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2010&d=0202&f=column_0202_004.shtml
"多くの企業で中国調達を推進する目的は、ほぼ100パーセント、コストダウンだろう。ところが、中国調達をはじめるとコストダウンが止まるという驚くべき事実がある。
コストダウンとは、それまで100円で調達していた部品を100円未満で調達することである。中国調達によるコストダウンの場合、同じ部品を日本国内で生産した場合との価格差をコストダウン額と称する場合があるが、調達先を日本国内サプライヤーから中国サプライヤーへ転注した初回は、いわゆるコストダウン額と同一であるが、2回目(翌年度)からは、コストメリットとして区別して考えなくてはならない。
日本のものづくりでは、同じ部品の調達コストは年々低下するのが当然であると考えられている。実際は人件費や原材料費の上昇と相殺され、表面価格は不変であったり上昇したりすることもあるが、製造工数や製造ロスは確実に減少していく。つまり同じものを繰り返し製造する過程で、作業に慣れ無駄な動きやミスが減少し、また冶工具の開発・改良が繰り返されていくというのがロジックである。これは何も日本特有のことではない、欧米でも、中国でもあることだ。但し工程改善力の多くは、現場力に根差す部分が大きいから日本の製造業が得意とすることは言うまでもない。一方、VA・VEでは欧米メーカに一日の長があり、中国サプライヤーがVA・VEで極端に後れを取っていることは否めない。
上述のように、中国はVA・VEにおいては技術的蓄積がまだ浅く、また人件費の安さがそれを阻害するとともに、製造業が依然として加工受託的形態が主流を占めていることから立ち遅れている。しかし、加工受託の中でも確実に育まれるはずの工程改善が、中国サプライヤーで進まない、あるいは立ち遅れているのはなぜだろうか。
製造委託部品の品質レベルで、及第ギリギリを60点としたら、日本のサプライヤーであれば、新規受託後早々に80点レベルに達する。一度80点レベルに達してしまえば、それを維持するのはさほど難しいことではない。サプライヤーのエンジニアのエネルギーは、工程の効率化へ振り向けられる。
一方、中国サプライヤーの場合どうだろうか。多くは及第ギリギリの60点に達したことで、移管(転注)スタートとなる。これは早期にコストメリット効果を発生させたいというバイヤー側の事情と、早期に売上に繋げたいというサプライヤー側の事情とが一致することによるのであるが、及第点ギリギリというのはまことに危うい。ちょっと気を抜いたり、何かのマイナス要因があったりすれば、たちどころに及第点を下回り不良品の山を作ってしまうから、サプライヤーのエンジニアはもちろん、バイヤーまでもが60点レベルの維持にエネルギーを投じることになるので、工程の効率化にまでエネルギーは振り向けられない。
仮に苦労の末80点のレベルまで品質を引き上げたとしても、日本のように工程効率化へエネルギーを向けられるかと言うと、残念ながら多くは否である。なぜなら中国は人材の流動化が激しいことに加え、経験から得られたスキルが個人に囲い込まれ、組織に技術が蓄積しない土壌であるからである。ゆえに現状維持にバイヤー、エンジニアのエネルギーが費やされてしまうのである。
そもそも経営層にも日々工程の改善、効率化をして製造原価を圧縮しなくてはならないといった認識が希薄である。当初100円の価値のあったものが、時間経過とともに90円になってしまうことを理解していない。「なぜ、同じ品質、機能を有するものが?」といった疑問が先に出てくる。むしろ人件費が上昇すれば、ものの価値も上昇すると考えているふしさえある。
今後、中国の人件費、人民元は確実に上昇して行く、その上昇分をそのまま価格に転嫁していたら確実に中国製造業の価格競争力は減退し、「世界の工場」という看板を返上することになる。そうならないためには、もっとひたむきに、足元の改善に本気で取り組める土壌を作っていかなくてはならないだろう。"
まぁ、これなんか中国で活動している人しか分からない実情ですよね。
日本のマスコミは中国や韓国を割に賛美してますけど、進出する企業にとって欲しいのは、こう言った情報ではないでしょうか。
- 重要なお知らせ 一覧