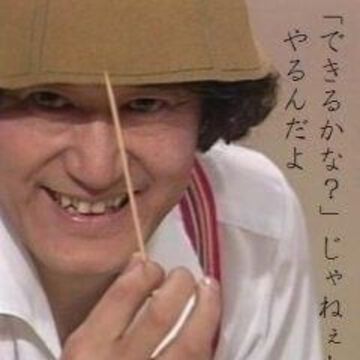http://blog.livedoor.jp/kazu_fujisawa/
金融日記さん
2012年、日本は世界で最も洗練された自由市場経済の国に生まれ変わる
最近はネットでも新聞でも日本はもうダメだという論調が多いですね。
今の政治をみていればそのように思う気持ちもよくわかります。
また、平成22年度の予算案は戦後初めて新規国債の発行額が税収を上回り、このままでは近い将来にデフォルトかハイパーインフレによる財政破綻は避けられないのではないかと思われます。
しかし、経済学者や市場関係者の間では、この日本のGDP比で200%を超えつつある政府債務が、いったいどのようなかたちで着地をするのかということに関して、実はあまり具体的なコンセンサスができていません。
池田信夫氏などはハイパーインフレといっていますが、竹中平蔵氏などは大増税の可能性を強調しています。
しかし、少なくとも現在のマーケットはハイパーインフレを織り込んではいません。
民主党政権の政策をみていたら、このペースでいけばあと5年ももたないと思われますが、日本はまだまだ増税の余地があるのも事実です。
というのも消費税が5%で世界の平均に比べれば非常に低い上に、中小零細企業はほとんど消費税を払わなくてくもよい仕組みになっているからです。
消費税を25%ぐらいに引き上げて、売上げの少ない中小企業にもきっちりと消費税を払わせれば、まだまだ政府債務の発散は食い止められるでしょう。
もし財政破綻がそこまで確実なら、いくら景気が低迷していて資金需要がないとはいっても、さすがに長期金利が1%台には留まっていないでしょうし、為替レートももっと円安になっているはずです。
もちろん、ハイパーインフレというのは予想が自己実現的なので、そのようなコンセンサスが形成されるのと、その実現はほぼ同時に起こるはずで、ある日突然一気にクラッシュするということも大いに考えれられますけれども。
このように、専門家の間では、ハイパーインフレか大増税かで意見が割れているようですが、実は、僕自身はかなり異なった楽観的シナリオを思い描いています。
というのも2012年あたりから日本の社会構造に大きな地殻変動が生じると思うからです。
日本の人口分布を見ていただければ、現在61歳から63歳ぐらいのところに突出したピークがあることがわかります。
約1000万人の塊です。
いうまでもなく戦後のベビーブームの1947年から1949年までの3年間の間に生まれた「団塊の世代」です。
日本の戦後の高度経済成長を引っ張ってきた原動力でもあり、最近では大企業での年功序列・終身雇用による強大な既得権益をにぎっており、イス取りゲームのイスをひとりで何個も占領し、1970年以降に生まれた若者に就職氷河期の苦渋を舐めさせた張本人でもあります。
団塊の世代は、よくも悪くも日本の政治や経済にもっとも大きな影響力を持っている世代なのです。
実際、日本の政治家で力を持っている人をみてみると大体65歳前後のかなりの高齢になっていることがわかるでしょう。
団塊の世代が安心して政治を任せられるちょっと上の先輩だとこのぐらいの年齢になるのでしょう。
また、ホリエモンや村上ファンドの村上世彰氏のような人物に拒絶反応を示したのも団塊の世代の一部の権力者だったのではないでしょうか。
彼らは日本の大企業や政治の権力の中枢に鎮座しており、そこにズカズカと踏み込んでいったホリエモンや村上氏のような人間を叩き潰したとも考えられます。
いくら日本の経済を考えると雇用の流動化が必要だといっても、硬直した雇用制度からもっとも恩恵を受けている団塊の世代がいる限り、政府がそのような政策をとることはありません。
テレビ局を買収しようとしたり、会社の資産の上にあぐらをかき企業価値を創造できない経営者に退場を迫った、ホリエモンや村上氏が、東京地検特捜部に些細なことで突然に逮捕されてしまったのも、ある意味、必然だったのかもしれません。
そういった会社の経営者がまさに団塊の世代なのです。
そして団塊の世代は、あと数年で莫大な退職金を受け取り、公的年金を満額支給されながら、日本経済の破綻から逃げ切ろうとしています。
このような日本で最も強い政治力を持っている、彼らの既得権益を脅かせば、政治的には無事ではすまないでしょう。
民主主義とは端的にいって多数派が少数派を搾取する仕組みに他なりません。
そしてその多数派の頂点に立っているのが団塊の世代なのです。
さて、なぜ僕があと数年で日本が劇的に変わると思うのでしょうか?
それはこの団塊の世代が2012年ごろから年金生活者になるからです。
おそらく満額の退職金を受け取り、かなり資産リッチな年金生活者になるでしょう。
その上、2012年ごろはまだ日本の財政も破綻はしていないと思われるので、満額の年金も支給されることになります。
世界的にみて、これほどの人口の裕福な年金生活者が突如と現われた例は他にありません。
だったら社会保障費がますます増大して、日本経済はさらに悪くなるだけじゃないかと思われるかもしれません。
しかし、僕は、団塊の世代の立場が劇的に変化することが、実はものすごく大きなインパクトを持ちえると思うのです。
現在の団塊の世代は、多くの企業でかなり高給をもらい、あと2年ほどで満額の退職金を受け取れるという状況です。
また、日本の大企業の経営者の多くもこの世代です。
つまり、彼らは労働市場や経営者の市場で、強大な既得権益を持っているのです。
それゆえ、ホリエモンのような若いチャレンジャーや、村上氏のような物言う株主は、自分の立場を危うくする脅威なのです。
閉塞感あふれる現代の日本で、若者がホリエモンや村上氏を熱烈に支持していたのも偶然ではありません。
閉塞感を作り出しているのが団塊の世代の既得権であり、就職氷河期などで若者はその一番の犠牲になっていたからです。
その閉塞感を打ち破るのが、ホリエモンや村上ファンドだったのです。
日本の政治家や検察などは団塊の世代の権益を守るディフェンダーだと考えれば、最近のおかしな政治や司法の流れも理解できるのではないでしょうか。
さて、ここまで読んでまだ劇的な社会構造の変化に気付きませんでしょうか?
この団塊の世代が今にぎっているのは労働者であり経営者としての権益であり、これが2012年から資本家としての権益に突然切り替わるのです。
年金生活者とは、いってみれば日本株式会社の配当を受け取っている投資家です。
日本経済が破綻すれば年金もなくなるので、自らの生活基盤も一夜にして崩壊するでしょう。
年金の原資はGDPに税率をかけたものに他なりません。
つまり、利害としては日本全体に長期的に投資している資本家そのものになるわけです。
資本家とはもっとも冷徹に経済合理性を追求しなければいけない人たちです。
2012年に、日本は「資本家」が政治でマジョリティーになるという世界で唯一の先進国になるのです。
団塊の世代は現在は労働者や経営者としての権益をがっちりとにぎっているので、解雇規制の強化や資本市場の規制強化によって自らのポジションを強固に守りとおそうとしています。
しかし、そんなことをしていてはいずれ国の経済が衰退することは、彼らが一番よくわかっています。
そして、彼らが年金生活者になると、いっぺんに立場が180度切り替わるのです。
資本家となった団塊の世代にとって、硬直した労働市場や、無能経営者を追い出せない資本市場など「悪」以外の何者でもありません。
また、年金生活者にとって物価が上がることも「悪」以外の何者でもないので、ゼロ金利でマネーをジャブジャブにしている金融緩和はとても容認できるものではありませんし、国家の財政規律というのは何にもまして重視されることになるでしょう。
インフレというのは年金生活者にとって最悪の経済現象だからです。
すると非常に奇妙な利害の一致が起こることがわかります。
資本家となった団塊の世代にとって、既得権で硬直してしまった日本の産業構造を創造的に破壊していく、ホリエモンや村上氏のような人物は、まさに救世主になるのです。
反面、働く能力があるのに働かず、社会福祉に寄生する若者や、そういった若者を先導する一部の社会主義運動家は、もっとも忌み嫌われる人間になるでしょう。
福祉のパイは限られているからです。
ソ連の崩壊、カンボジアやルーマニアの社会主義政権による市民の大虐殺、旧東ドイツの経済的困窮とベルリンの壁崩壊・・・
こういった社会主義思想の恐ろしさを身をもってみてきたのも団塊の世代です。
それでも少子高齢化で、年金生活者と彼らを支える労働者の比率はどんどん悪化してしまうだろうと思うかもしれません。
しかし、これについても実はまったく心配はありません。
世界的に「人間」ほどあまっている資源はないからです。
日本が財政破綻しなければ、そんなものは輸入しようと思えばいくらでも輸入できます。
日本の文化がうんたらかんたらとかいう抽象的な議論など、移民をどんどん受け入れれば、団塊の世代の介護やメイドなどのサービスがどれほど安価になるかを考えれば、一気に吹き飛ぶでしょう。
資本家である団塊の世代にとってマクロな経済成長が重要なのであって、その中身がどうなっていようとあまり関心はありません。
極端な話、多国籍企業を率いる経営者や、莫大な金額を運用するファンド・マネジャー、世界的なスキルを持っている一部のエンジニアや科学者などには、何百億と給料を払ってあげたいと思うだろうし、中国などの新興国と競争しなければいけない単純労働者の給料は年50万円程度で十分だと思うでしょう。
団塊の世代のせいで就職できずに、付加価値の高いスキルを身に着けられなかった若者は、中国や東南アジアの単純労働者と同じ給料で働かされるのは、ある意味、当然の報いでしょう。
日本は、アメリカよりも、もっとアメリカ的な社会になる可能性があるのです。
2012年ごろには、日本は世界でも稀にみる、先鋭的な自由市場経済の国に突然のように変貌を遂げるでしょう。
(この話のオチとして、その結果、GDPは成長するけれども超格差社会の荒廃した社会になると思いきや、実は福祉に回せるパイが増大し、世界でも稀にみる弱者にやさしい社会になっているかもしれません)
僕の予想が正しいとしたら、今のおかしな社会主義政策のオンパレードも、あと2、3年の辛抱かもしれません。
僕は、新年そうそう、その可能性に賭けてみようと思います。
☆
為替と米国市場次第でしょうが当分は
BULLな感じかなあ。
日経225ETFは色々あるけど、お薦めは
なんだろう??
あんまり連動しないんですよねえ。
それよりこれからはTOPIX連動が上げかな??
2件のコメントがあります
1~2件 / 全2件
10年の中国経済成長率、9.5%の見通し=国務院
[北京 1日 ロイター] 中国政府のシンクタンクである国務院発展研究センターは、2010年の中国経済成長率について、不動産投資が成長を支援するとともにインフレが引き続き抑制されることから、9.5%となり前年を上回るとの見通しを示した。研究員Zhang Liqun氏によるリポートが1日付の中国経済時報に掲載された。
リポートは「2010年の海外の(経済)環境は引き続きかなり厳しいが、これ以上悪化はしないだろう」と指摘。
「十分な生産と供給を背景に2010年は顕著なインフレは見られない見込み」とし、同年の消費者物価指数(CPI)上昇率は3%以下にとどまるとの見通しを示した。
4兆元規模の刺激策に加え、銀行融資の急増により、09年第3・四半期の中国国内総生産(GDP)伸び率は前年比8.9%となった。
リポートは、今年、政府の刺激策の効果が薄れる一方で、不動産投資が前年比30―40%増加し「投資の伸びをけん引する」可能性があると指摘した。
[北京 1日 ロイター] 中国政府のシンクタンクである国務院発展研究センターは、2010年の中国経済成長率について、不動産投資が成長を支援するとともにインフレが引き続き抑制されることから、9.5%となり前年を上回るとの見通しを示した。研究員Zhang Liqun氏によるリポートが1日付の中国経済時報に掲載された。
リポートは「2010年の海外の(経済)環境は引き続きかなり厳しいが、これ以上悪化はしないだろう」と指摘。
「十分な生産と供給を背景に2010年は顕著なインフレは見られない見込み」とし、同年の消費者物価指数(CPI)上昇率は3%以下にとどまるとの見通しを示した。
4兆元規模の刺激策に加え、銀行融資の急増により、09年第3・四半期の中国国内総生産(GDP)伸び率は前年比8.9%となった。
リポートは、今年、政府の刺激策の効果が薄れる一方で、不動産投資が前年比30―40%増加し「投資の伸びをけん引する」可能性があると指摘した。
米GDP伸び率、今後10年間は年2%以下に=エコノミスト
[アトランタ 3日 ロイター] 3日に開催された米国経済学会(AEA)の年次総会では、著名エコノミストの多くが、米国の国内総生産(GDP)伸び率は向こう10年間、年2%を下回るとの見通しを示した。
厳しい雇用情勢や不動産セクターの不振、依然としてぜい弱な銀行業界を理由に、米経済成長は抑制されるとの見方が大勢となった。
ハーバード大学の教授で、全米経済研究所(NBER)前所長であるマーチン・フェルドシュタイン氏は「住宅や商業用不動産が低迷したままの状況下では、力強い景気回復は難しいだろう」との見解を示した。
住宅市場は今回の金融危機から大きな打撃を受け、住宅価格(中央値)は2005年のピークから30%以上下落。これに伴い、米経済の主なけん引役である消費者の貯蓄志向が強まり、消費支出が減少した。
コロンビア大学教授でノーベル経済学賞受賞者のジョセフ・スティグリッツ氏は「消費に代わるものを見つけるのは極めて困難」と述べた。
ハーバード大教授のケネス・ロゴフ氏は、政府が銀行支援をやめれば新たな破たんが起きると指摘。「銀行の今の利益は幻想だ」と述べた。
[アトランタ 3日 ロイター] 3日に開催された米国経済学会(AEA)の年次総会では、著名エコノミストの多くが、米国の国内総生産(GDP)伸び率は向こう10年間、年2%を下回るとの見通しを示した。
厳しい雇用情勢や不動産セクターの不振、依然としてぜい弱な銀行業界を理由に、米経済成長は抑制されるとの見方が大勢となった。
ハーバード大学の教授で、全米経済研究所(NBER)前所長であるマーチン・フェルドシュタイン氏は「住宅や商業用不動産が低迷したままの状況下では、力強い景気回復は難しいだろう」との見解を示した。
住宅市場は今回の金融危機から大きな打撃を受け、住宅価格(中央値)は2005年のピークから30%以上下落。これに伴い、米経済の主なけん引役である消費者の貯蓄志向が強まり、消費支出が減少した。
コロンビア大学教授でノーベル経済学賞受賞者のジョセフ・スティグリッツ氏は「消費に代わるものを見つけるのは極めて困難」と述べた。
ハーバード大教授のケネス・ロゴフ氏は、政府が銀行支援をやめれば新たな破たんが起きると指摘。「銀行の今の利益は幻想だ」と述べた。