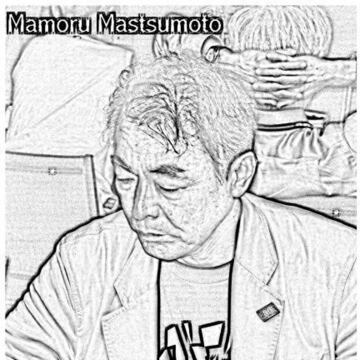久しぶりに東京に行った。ついでに新国立劇場小劇場で福田善之作、宮田慶子演出の『長い墓標の列』を観た。
ドラマの舞台は東大経済学部教授河合栄治郎をモデルに、わが国が戦時下に突入して行く昭和13年から19年の大学の自治、学問の自由が犯されていく過程の中で、誠意あるインテリが如何に戦い、そして敗れたかを描いている。
第一幕が大学の経済学部研究室、第二幕、第三幕が山名教授の自宅書斎なので、人物の動きより、一つ一つの台詞が命、時代は違えど問題は現代が抱える問題に重なっています。翔年は戦後の学生運動の激化するなかで、インテリの教祖的存在であった高橋和巳が京大キャンパスで戦い苦しんだこととも重なり、何時の時代にあってもこのような大問題は構造的にくり返されると思いました。
もう一つ感じたことがあります。それはこのような問題は何時の時代でも起こりうること故、インテリは絶えず真剣に議論を深めていなければならないという事でした。。スポーツマンが筋肉や反射神経を極限まで鍛えぬき同時に精神も鍛えるように、思想もまた同じように、議論を戦わせ、競い合い、その過程で精神も鍛えぬいていなければならないと感じました。そうでないと社会に及ぼす力になりえないと。それでもなお、インテリは政治行動は不得意なので、国家や社会に対して如何に向き合い、影響力を行使できるのか。いや、効果的な影響力の行使などありうるものなのか? 気づかされ、考えさせられました。
観終わった後、充実感がのこった演劇でした。
※参考、Wikipediaの河合栄治郎
いつも『もの言う翔年』を読んでくださりありがとうございます。お陰さまで「政治評論」も「囲碁」もランキング上位に入っております。コメントをいただいたり、ランキングがそこそこにとどまっているのを励みにBlogを書いております。お暇なときに見てください。にほんブログ村にほんブログ村