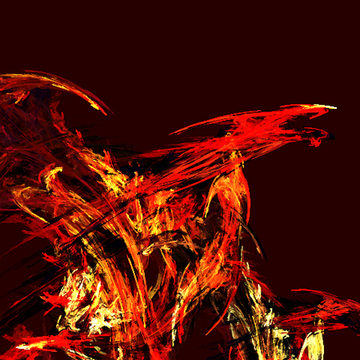…なんだかなぁ。
http://sankei.jp.msn.com/economy/news/120729/biz12072920350003-n1.htm
”欧州債務危機の深刻化にともない再び円高基調が強まるなか、「為替デリバティブ」と呼ばれる金融派生商品により多額の負債を抱えて経営難に陥る中小企業が続出している。ドルに加え、ユーロや英ポンドに対する円高で損失が膨らむケースが増加。同商品による損失で倒産した企業の数も、前年度を上回るペースとなっている。
為替デリバティブは、あらかじめ取り決めた為替レートで外貨を売買する契約。モノを輸入し、ドルなど外貨で決済する場合、円安が進むと購入コストが増える。このため例えば1ドル=100円で買う契約を銀行と結べば、それ以上円安が進んでもコスト増にはならない。
だが、逆に円高に進み1ドル=80円となった場合は、輸入業者に20円分の損失が発生する。問題の商品は、平成20年秋のリーマン・ショック前に、取引先の銀行から「円安になった場合のリスクを回避できる」と勧誘され、5年や10年単位で契約したものが多い。このため最近の円高で、毎月の決済のたびに損失が膨らんでいる。
帝国データバンクによると、今年上期(1~6月)に「為替デリバティブ契約に伴う損失」で倒産した企業は、前年同期の11件を上回る16件(負債総額1千万円以上)。毎月1千万円以上の損失を出し、負債総額が50億円超にのぼった大型倒産が、6月に立て続けに発生した。
為替デリバティブ問題に詳しいアディーレ法律事務所(東京都豊島区)によると「ユーロやポンドの契約で損失が拡大し、相談に来るケースが増加している」。裁判外紛争解決手続き(ADR)の申し立て件数も「大きく増えている」(金融筋)という。”
どう突っ込めば良いんでしょうね。リスクを甘く見ていたって事でしょうか。
リスク管理の為の為替デリバティブで死ぬなんて本末転倒な気がしますが。
しかし、なんでそんな長期契約なんだろう。
やはりどっかで儲けようってスケベ根性が有った気が…。
…後、金融商品なんて長期的に見て取引を持ちかけている相手が勝つものだと思うけど。
その辺の認識が欠けていたとしか思えないなぁ。
…なんにせよ。ご愁傷様って事で。