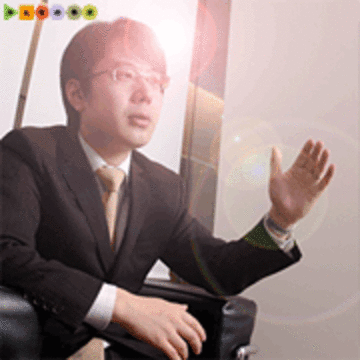【投資脳のつくり方】ジュグラー循環、過大融資が危機のシグナルに
■いつも「投資脳のつくり方」をお読みいただき、ありがとうございます。
私、経済アナリスト、木下晃伸(きのした・てるのぶ)のアシスタントを務めております、佐々木さと美と申します。
木下が行う取材準備から、業務運営に関わることまで幅広く仕事をしております。
昨日より、当メールマガジンの配信から広報・PR業務も担当させていただいております。
読者のみなさまと一緒に成長していきたいと思います。今後ともどうぞよろしくお願いいたします!!
2009年1月7日(水)本日お伝えする内容はこちら!
1.【世界】ジュグラー循環、過大融資が危機のシグナルに
2.【日本】環境市場、5年で100兆円
3.【世界】セカンドライフの誤算
1.【世界】ジュグラー循環、過大融資が危機のシグナルに
(出所)2009年1月7日付日本経済新聞朝刊25面より
●三菱UFJ証券、嶋中雄二先生のバックボーン
●景気循環について改めて過去の英知を学ぶ
●恐慌は、特異なものではなく、循環の一形態にすぎない
昨日、経済評論家、三原淳雄先生主催の勉強会に参加させていただく機会を得た。隔月で1回開催されるのだが、今回のゲストスピーカーは、三菱UFJ証券、景気循環研究所所長の嶋中雄二先生であった。嶋中先生は、UFJグループ時代からミーティングに参加させていただく機会を多く持っていた。そのデータ量、即時性、時代を幅広く見る目など、示唆溢れる内容にいつも驚かさ
れていたものだ。
その嶋中先生が中心となって、現在日本経済新聞でゼミナール「景気循環と恐慌」を連載されている。私も、経済は嶋中先生が説かれるように循環しているという考えを持っている。大変参考になるコラムだと思う。知っていても、経験したからこそ分かる人類の知恵を今学ぶ時だと改めて考えさせられた。
●恐慌の持つ周期的性格を早くから指摘し、世界で初めて景気循環の一局面として「恐慌」を位置づけて分析したのが、19世紀フランスの経済学者ジュグラーである。彼は、仏・英・米三カ国の手形割引高、金銀などの金属準備、手形の流通高のデータの推移を分析し、そこに7-12年、平均10年の周期の景気循環現象を見出した。(中略)ジュグラーによると、この規則的なサイク
ルは、大産業が発展するための条件のひとつであり、戦争や革命、関税率の変更、公債発行、流行の変化、新販路の開拓といった様々な人為的・偶発的要因があっても、常に出現を繰り返す性質を持つ。後にシュンペーターによって「ジュグラー循環」と命名されることになるこの循環には、当時異なる金融システムを有していた仏・英・米の三カ国に、制度の壁をも越えて同時進行的に出現する際立った特徴があるという。
2.【日本】環境市場、5年で100兆円
(出所)2009年1月7日付日本経済新聞朝刊5面より
●環境ビジネスがさらに拡大
●息の長いテーマとなる
●国策に売りなし、と考え有望企業を探し出す努力をする
斉藤鉄夫環境相は6日、地球温暖化防止や省エネ促進などの環境対策を景気浮揚につなげる「日本版グリーン・ニューディール構想」(仮称)をまとめる考えを正式に表明した。次世代自動車や太陽光発電などの普及を通じ、2006年時点で70兆円だった環境ビジネスの市場規模を今後5年程度で100兆円以上に拡大するほか、220万人以上の雇用確保を目指す。関係省庁とも連携し、3月までに具体策をまとめる。
具体的には太陽光発電や省エネ家電の市場拡大などが柱になる見通し。必要な財源については10年度以降の予算で賄う予定だ。
金融危機を背景にした景気低迷を受け、各国も成長戦略の柱に環境対策を据えている。米国のオバマ次期大統領は太陽光や風力などの導入拡大に1500億ドルを投じ、500万人の雇用創出につなげる方針を表明。ドイツは再生可能エネルギー産業を20年までに自動車産業を上回る規模に育てる目標を打ち出している。
すでに、株式市場は環境に対する投資行動を促しているが、いまは投資テーマ不在の中で脚光を集めているという印象が強い。しかし、いずれ環境は大きなテーマに育っていくだろう。投資格言に「国策に売りなし」という言葉ある。国が向かう方向に注視することは、投資において非常に重要なことだ。
直近経験した恐慌でも、すでに経験していることだ。環境をテーマに、魅力ある企業を探し出していくことは、しばらく続く行動になる。
3.【世界】セカンドライフの誤算
(出所) 2009年1月7日付日本経済新聞朝刊1面より
●セカンドライフバブルが崩壊
●日本でも多くの有名企業が参画していた
●シンプルに面白いか面白くないか
リンデンラボの創業者フィリップ・ローズデール(40)がセカンドライフを立ち上げたのは2003年。現金と交換できる仮想通貨「リンデンドル」などを売り物に、世界中で空前のブームを巻き起こした。
仮想空間で人々が交流し、第二の人生を送る。その発想や、現金と交換できる通貨の存在、つまり、真正面からビジネスを捉えたことが、多くのベンチャー企業をセカンドライフに駆り立てた。また、日本でも、サマンサタバサなど有名企業が、仮想の街を作るという記者発表をしていたものだ。
だが、熱狂が冷めるのも早かった。無料会員は世界全体で1660万人と2年前の5倍以上に増えたものの、主力の有料会員は07年6月をピークに減少傾向をたどり、ついに8万人を割り込んだ。
これは、ごく自然な流れだと思う。日本経済新聞掲載記事にはいろいろと小難しいことが書かれているが、要は、使いづらく面白くない、ということだ
と思う。私は技術者ではないので、そんなことを軽々しく言う資格はないが、
いまやネットは操作性がきわめて重要なポイントとなっている。その点で、セカンドライフは使いづらくて仕方がない。
仮想空間にお金を払うより、現実世界はもっと面白い。そう考える人が世界中で多かっただけの話ではないだろうか。大衆は賢い。
- 重要なお知らせ 一覧