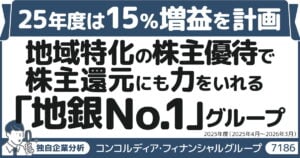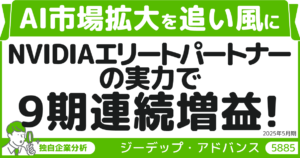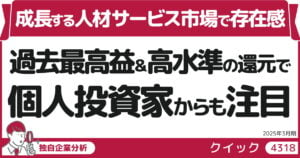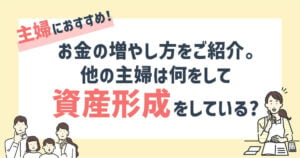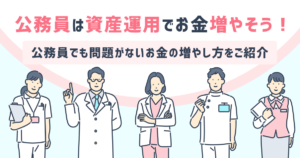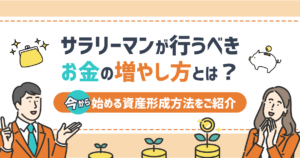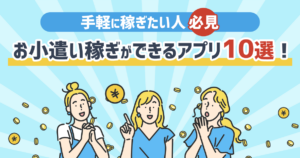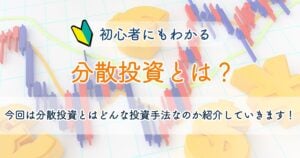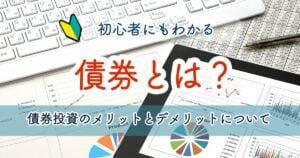ETFとは?特徴からメリットデメリットまで解説!

ひとこと解説
- ETFは株と同じように取引できる投資信託の一種
- 手数料のシステムも株と同様
- ETFはリアルタイムで取引が可能!
- 長期分散投資にはETFがオススメ!
話題の投資商品「ETF」
みなさんは投資においてよく耳にする「ETF」という商品についてご存知ですか?ETFは比較的新しい投資商品にも関わらず、短期間で大きな市場を築いてきた注目度の高い商品になっています。加えて、自分で個別に銘柄を選ぶことなく1本のETFでまとめて分散投資が行える点も支持されている理由の1つです。
しかし、「そもそもETFって?どんなメリットやデメリットがあるの?」といった疑問をお持ちの方も多いかと思います。そこで今回は、「ETFとはなんなのか、ETFのメリットとデメリット」を中心に解説していきたいと思います。
またETFと似た投資商品として投資信託がありますが、今回はETFと投資信託の共通点、異なる点も合わせて紹介します。
目次
そもそもETFとは?
ETF(イーティーエフ)とは「Exchange Traded Fund」の略で日本語表記では「上場投資信託」といいます。文字通り投資信託が証券取引所に上場をして、株式のように売買ができるようになったというイメージで間違いありません。そのため証券取引所が開いている時間であればリアルタイムで取引を行うことができます。
ETFの特徴は、いくつかの金融商品(株など)が組み合わさってできているものが多いことです。「詰め合わせ商品」と考えるとわかりやすいかもしれません。例えば日経平均に連動するETFを購入すると、それだけで日経平均株価を構成する225の全ての銘柄に投資したのと同じことになります。
このようにETFは様々な投資対象を一括で取引できるため、自動的に分散投資を行うことができます。分散投資は投資におけるリスクの軽減に有効な手段なので、そのメリットを受けられるETFは安定した金融商品であると言えます。
関連記事:分散投資とは
ETFってどんな種類があるの?
ETFの特徴を理解していただいたところで、次はETFの種類について紹介していきたいと思います。一口にETFといってもその種類は様々です。そこで今回は、主な7種のETFの特徴について簡単に紹介します。
| ETFの種類 | 特徴 |
|---|---|
| 株価指数連動型 | 日経平均株価やTOPIXなどに連動し、市場全体に投資ができるETFです。東証に上場しながらも、アメリカのダウ平均株価や中国の上海50指数に連動し、海外市場に投資可能なETFもあります。 |
| レバレッジ型 (ブル型※1) |
連動する指数の値動きよりも大きい値動きをするETFです。2倍や3倍の値上がり・値下がりをします。 |
| インバース型 (ベア型※2) |
連動する指数の値動きと反比例した値動きをするETFです。指数が下落した場合に値上がりします。 |
| REIT※3 (不動産投資信託) |
投資家から資金を募って不動産を購入し、そこから生じる賃料や売却益を投資家に配当する投資信託であるREITを集めたETFです。 |
| コモディティ (商品先物) |
金、銀、プラチナ、原油、穀物など個別の商品の値動きに連動するよう作られたETFです。これらの商品を先物市場で取引する場合よりも低コスト低資金で取引できるメリットがあります。 |
| 債券 | 債券指数に連動するETFです。比較的に価格変動リスクが少ない債券への分散投資ができます。 |
| テーマ型 | テーマによって投資対象を選択しているETFです。高配当の銘柄だけを集めたものや、金融業や鉄鋼業などの業種別に銘柄を集めたものがあります。 |
※1 ブル型とは指数の動きと比例するように構成されたETFを指します
※2 ベア型とは指数の動きと反比例するよう構成されたETFを指します
※3 REITとは、投資家から資金を募り「不動産」を購入し、そこから生じる賃料や売却益を投資家に配当する投資信託の一種です。
ご覧のとおりETFにはREITに対応するものから、コモディティに対応しているものまで豊富なラインアップがあります。ETFの豊富なラインアップのおかげでより多岐にわたる分散投資を手軽に行うことが可能になります。
また国内ETFの他に、「海外ETF」といって海外市場に上場しているETFもあります。これは、外国株の取引ができる証券会社であれば日本国内でも取引可能です。海外の株式市場に上場しているETFは、種類の豊富さ、本数とも圧倒的に多く、日本には存在しないようなものも多数あります。
ネット証券では、こういった魅力的な海外ETFを日本でも購入可能にすることに力を入れており、手軽に取引が行えるようになっています。
ETFと投資信託って何が違うの?
一般的な投資信託とETFとの違いはなんでしょうか。両者ともに投資家から集めた資金を用いて資産運用の専門家が運用を行う商品という点では共通していますが、もちろん異なる点もあります。
それでは、どんな違いがあるのか見ていきましょう。まずは下記の表をご覧ください。
| 投資信託 | ETF | |
|---|---|---|
| 取引できる価格 | 1日1回算出される基準価額 | 証券取引所での値動きを反映した市場価格 |
| 取引できる時間 | 販売会社により異なる | 証券取引所の開いている間 国内ETFの場合 9:00~11:30, 12:30~15:00 |
| どうやって購入するか | 証券会社・銀行・郵便局などの窓口や個別ページから | 株と同様に証券取引所から |
| 最低投資金額の目安 | 500円〜1万円前後 | 1万円前後~ |
| 信託報酬(運用経費としてかかるコスト) | ETFと比べるとやや高い | 投資信託よりも安い |
| 信用取引(※1)ができるか | × | ◯ |
※1 信用取引とは、現金や株式を担保として証券会社に預けて、証券会社からお金を借りて株式を買ったり、株券を借りてそれを売ったりする取引のことです。
関連記事:信用取引とは
上記の表の「取引できる価格」や「取引できる時間」からわかるように、投資信託とETFの大きな違いは「売買の自由度」です。
投資信託の価格は1日に1回決定される基準価額で取引されます。しかし基準価額が公表されるのは投資信託の取引の申込を締め切った後なので、投資家は当日の基準価額が分からない状況で投資信託の取引を行わなければいけません。そのため、自分が思っているよりも高く買い付けてしまったり、逆に安く売ってしまう可能性が出てきます。
一方、ETFは上場しているため上場株式と同様に市場価格で取引がされます。そのため自分が買い付けたい値段のときに買い付けられる確率が上がります。売却時においても同じことがいえます。加えてETFは、株式と同様に「指値・成行注文」(※2)が行えます。こうした取引における自由度は投資信託にはないETFの特徴といえます。
※2 指値注文とは、自分の取引したい価格を指定する注文のこと。成行注文とは、特に価格は指定することなくすぐに取引できる注文のこと。
次に、購入に必要な金額という面では投資信託の方が比較的リーズナブルに設定されています。そのためコツコツと少額で運用していく方は投資信託の方が相性がいいといえます。逆に比較的資金があるという方はETFと相性がいいといえます。
また、ETFは投資信託と比較して信託報酬が低く設定されています。信託報酬とは、ETFや投資信託を運用していくうえでかかってくるコストのことです。
投資信託の場合「証券会社や銀行などの販売元」「運用会社」「信託銀行」の三社に対して信託報酬を払います。一方でETFの場合「運用会社」「信託銀行」の二社のみに信託報酬を払うので結果的に信託報酬が低く設定することができるのです。
信託報酬は運用している間ずっとかかってくるコストなのでこのコストを低く抑えられるのはETFならではの特徴だといえます。
最後にETFには信用取引が行えるという特徴があります。信用取引は簡単にいうと「自分を信用してもらい、持っている資金以上の金額で投資を行うこと」です。信用取引が可能ということは、自分が持っている資金以上の金額を用いてさらに大きなリターンを狙えるということになります。
しかし、信用取引は自分の資産力を十分考慮したうえで行わないと買い付けたETFの価格が急落したときに、大きな損害を被ってしまう可能性があります。そのため、信用取引はメリットも大きいがリスクも大きいということを忘れないようにしましょう。
以上が代表的な投資信託とETFの違いになります。
国内ETFと海外ETFの違い
「ETFってどんな種類があるの?」でも少し紹介した海外ETFですが、国内ETFとはどのような違いがあるのでしょうか。こちらも以下の表と合わせて見ていきましょう。
| 国内ETF | 海外ETF | |
|---|---|---|
| メリット | ・日経平均やTOPIXといった馴染みのある指数が多い ・日中にリアルタイムでの取引が容易 ・為替変動リスクが低い |
・ETFの種類が豊富 ・ETFの市場規模が日本よりも大きいため、流動性が高いものが多い |
| デメリット | ・ETFの種類が海外に比べると少ない ・流動性の低い銘柄が多い |
・時差があるため国によってはリアルタイムでの取引が難しい ・国内ETFと比べて売買手数料が割高 ・為替変動リスクがある |
国内ETFは、表からも分かるように馴染みのある指数と連動するものが多く、海外ETFに比べて特に投資初心者の方には扱いやすいといえます。またリアルタイムで取引が簡単にできるのでその点も国内ETFのメリットといえます。
しかし、国内ETF市場は海外市場に比べると発展途上であり商品数や市場規模という面では遅れをとっています。そうはいっても、中長期的な運用を考えている投資家の方でしたら国内ETFは魅力的な商品だといえます。
海外ETFは市場規模が大きく、商品数も豊富なため様々なETFに投資できるというメリットがあります。また様々な地域の海外ETFを買い付ければ、国際分散投資の効果もグッと上がります。
もちろん国内ETFにも、海外の指数に連動するETFは多数あるため、国際分散投資は可能です。しかし、国内ETFが扱う海外指数連動ETFの種類は海外ETFに比べて少ないことに加え、出来高が少ない銘柄が多いため取引しにくい面があります。
こうした点を考えると、国際分散投資を長期的に行いたいと思っている投資家の方は海外ETFの方が向いているといえます。
しかし、海外ETFにもデメリットがあります。その中でも「売買手数料が高い」「為替変動リスクがある」という点には注意したいところです。まず売買手数料ですが国内ETFと比べて割高に設定されています。そのため売買を頻繁に繰り返すと利益の確保が難しくなってしまいます。
次に「為替変動のリスク」について説明します。海外ETFの取引通貨は外貨(主に米ドル)となるため、買い付けた海外ETFを円換算する際に為替差損が生じる可能性があります。
うっかり円高のときに買い付けた海外ETFを円安のときに売却してしまったら為替差損で利益が減少してしまいます。それどころか、現地通貨ベースでは利益が出ているにもかかわらず、円ベースでは損失ということすらあります。
こうした「為替変動」にも気を配る必要があるのが海外ETFのデメリットといえます。
自分の投資スタイルにあっているのは「国内ETF」なのか「海外ETF」なのかしっかりとそれぞれのメリット、デメリットを考えたうえで買い付けるよう心がけましょう。
注目度の高い海外ETFを購入可能なネット証券
最後に、海外ETFが購入可能なネット証券をいくつか紹介します。
| 会社名 | 1米ドルあたりの為替手数料(またはスプレッド) |
|---|---|
| SBI証券 | 0.25円 |
| 楽天証券 | 0.25円 |
| マネックス証券 | 0.25円 |
| DMM株 | 0.25円 |
ETFのメリット・デメリットとは?
ここまでETFの特徴、主な種類そして投資信託との違いについて解説してきましたが、ここからは、ETFのメリットデメリットを紹介していきます。
投資において投資商品のメリット、デメリットを正しく把握することはとても重要なことです。ETFに限らずどの投資商品においてもメリット、デメリットをしっかりと把握するようにしましょう。まずは4つのメリットから見ていきます。
メリット1:自分の好きなタイミングで売買が可能!
最初にあげられるメリットとしては、「売買のタイミングの自由度が高い」ことがあげられます。ETFは上場している投資信託なので株式と同様に証券取引所が開いてる時間であれば何度でも売買を行うことができます。そのため常に変動する市場価格で取引をすることができます。また、株式の取引でお馴染みの「指値・成行注文」も行うことができます。
こうした取引における自由度は通常の投資信託にはないETFのメリットだといえます。取引のルールが基本的に株と同じなので、特に株式の取引をしたことがある方にとって取り引きがしやすい商品になっています。
メリット2:信託報酬が低く設定されている
つづいてのメリットとして、信託報酬が低く設定されていることがあげられます。信託報酬とは、取引手数料とは別途かかる、ETFや投資信託を運用していくうえで必要になるコストのことです。
長期運用を考えた際に、信託報酬などのランニングコストを吟味することは非常に重要になってきます。なぜなら、塵も積もれば山となるというようにたとえ小さな金額の手数料であっても運用を続けていくうちに大きな金額になってしまうからです。
その点ETFの信託報酬は投資信託と比較して低く設定されていることが多いので、ランニングコストを抑えることができます。こうした低コストでの運用に向いているという点もETFの大きなメリットです。
メリット3:少額で分散投資が可能
ETFのメリットはまだまだあります。冒頭でも少し触れましたが、ETFは少ない資金量でも分散投資をすることが可能になっているのです。
「つまりどういうことなの?」と思っている方もいらっしゃると思うので、簡単に説明していきます。そもそもETFとは、特定の指数に連動するように構成された商品です。特定の指数を構成している株式またはその他金融商品を集めてパッケージ化した金融商品というイメージです。
通常の株取引で特定の市場全体に投資をしようとしたら、かなり大きな金額と労力が必要になってきます。日経平均を例に考えてみましょう。日経平均株価は計225銘柄で構成されています。この225銘柄それぞれに分散投資をしようとすると配分の考慮はもちろんのこと多額の資金調達が必要になってしまいます。
しかし、日経平均に連動するように構成されたETFを1本買うだけで、構成銘柄225本に分散投資したのと同じ効果が得られるのです。しかもETFは2万円前後から購入が可能になっているのでいかに低コストで分散投資を行うことができるか理解できたかと思います。
この少額から様々な市場に対してこの少額から様々な市場に対して手軽に分散投資ができるのはETFの大変魅力的なメリットです。手軽に分散投資ができるのはETFの大変魅力的なメリットです。
メリット4:銘柄が選びやすい
最後のメリットは、「銘柄の選びやすさ」です。個別株式の場合は企業分析などを入念に行い買い付けたい銘柄を選定する必要があります。さらに個別株式で分散投資を行うとしたらさらに労力が必要になってきます。投資初心者が挫折してしまう要因の1つがこの「銘柄選び」だといえます。
その点ETFは特定の市場の指数に連動しているため、「日経平均」や「TOPIX」などニュースなどで馴染みのある指数に連動したETFを買い付ければ各々の細かい企業分析をする必要はなく、基本的に日本経済全体に関するニュース、TV、新聞やネットを気に掛けることで運用していくことができます。各企業のニュースを追うことと比べ、日本経済全体に関するニュースを追うことは比較的実行しやすいと思います。
こうした、「銘柄の選びやすさ」もETF特有のメリットだといえます。
ETFの3つのデメリット
つづいてETFのデメリットを見ていきましょう。どんなものでもメリットがあればデメリットが存在します。そのためこれから紹介するデメリットをしっかり理解して「どうカバーするか」を考えることが非常に重要です。
デメリット1:価格の乖離が起こることがある
1つ目のデメリットとして、ETFは「価格の乖離」と呼ばれることが起こる可能性があります。ETFには、上場株式としての「市場価格」と投資信託としての「基準価額」の2つの価格があります。
「市場価格」は市場の需要給供で決まり常に変動しますが、投資信託の価値である「基準価額」は1日1回取引終了後に決定されます。つまり日中の取引の間、株式としての価値は変動し続けるが投資信託としての価値は取引が終わるまで前日の基準価額に固定されたままになってしまうのです。
その結果、本来の投資信託としての価値よりも高い市場価格が付けられたり、逆に本来の投資信託の価値よりも低い市場価格が付けられる可能性が生まれるのです。この「市場価格」と「基準価額」の差のことを価格の乖離と言います。例としてグラフを用意したので合わせて参照ください。

そのため、基準価額と市場価格をしっかりと比較して取引をしないと損をしてしまうリスクがあります。たとえば、基準価額よりも低い市場価格の時に売りを行ってしまうと、「本来ならもう少し高く売れたのに…」というような結果になってしまう可能性もあるので注意が必要です。
デメリット2:分配金が自動的に再投資されない
2つ目のデメリットとしては分配金が自動で再投資されないことがあげられます。分配金とは、投資信託・ETFの収益から投資家に支払われるお金のことです。ETFの分配金が支払われる頻度は年1回、年2回、年4回というように各ETFごとに決められています。投資信託であればこの分配金を「受け取りをする」か「再投資する」かを選ぶことができますが、ETFでは受け取ることしかできません。
つまり、分配金を再投資したい場合はもう一度手動でETFの買い付けを行わなければなりません。さらに最低購入金額まで分配金を貯めて、売買手数料を払って…と様々な手間が必要になってしまいます。そのため、分配金を自動で再投資できない点はETFのデメリットだといえます。
デメリット3:売買時に手数料がかかる
3つめのデメリットは、「売買時に手数料がかかること」です。投資信託であればノーロード信託といって売買手数料のかからないものもありますが、ETFは上場株式と同じく売買の際に手数料が必要になってきます。
運用コストが低いことがETFの魅力の1つですが、頻繁に売買を繰り返すと各取引時にかかる手数料がかさんでしまい、運用コストが低いという恩恵が薄れてしまう可能性があります。これもETFのデメリットの1つです。
ETFにオススメの証券会社4選!
だんだんとETFの特徴が掴めてきたころではないでしょうか。しかし、「じゃあ一体どの証券会社でETFを買えばいいの?」と疑問に思っている方もいると思うので、最後にETFを運用していくのにオススメの証券会社を4社紹介していきます。
SBI証券 - いろんな地域の国のETFが購入可能!
初めに紹介するのは、口座開設数でトップクラスの実績を持っているSBI証券です。海外ETFを広く取り扱っており、人気の米国から新興国まで幅広い地域の海外ETFを買い付けることができます。そのため様々な国への地域分散投資が可能になり、リスク低減を測ることができます。

さらに、SBI証券では大変便利なサービスが充実しています。買い付けたい海外ETFを調べるときに便利な検索機能や、分かりやすい海外ETFの買付方法など、投資初心者の方でも安心できるサービスが充実しています。
そのほかにも銘柄選びをサポートしてくれるロボアドバイザーや貸株サービス、定期買付サービスなど、初心者からベテランまで全投資家をサポートしてくれる環境が整っています。米国に限らず様々な地域のETFを運用していきたい、今後は外国株式の取引も考えているという方はSBI証券が特にオススメといえます。
au株コム証券 - 手数料無料の「フリーETF」
ETFといえばauカブコム証券と言われるほど、ETFにおいて優位性の高いauカブコム証券。その大きな理由として「フリーETF」と呼ばれる、手数料が無料のETFを現物取引では100銘柄取り揃えています。信用取引に至っては全銘柄対象という大盤振る舞いです!

またフリーETF対象銘柄は以下の項目をクリアしたものに限られ、安定した商品を取り揃えているため、多くの投資家から支持されています。そのためフリーETFなら投資初心者の方でも手数料で利益が圧迫される心配もなく、安心して運用していくことができます。
・個人投資家のETF取引活性化に資するか
・商品設計(連動する指数が主要な指数であること、複雑かつ高リスクでないもの等)
・取引機会(流動性)が十分に確保されているかなど
加えてフリーETF対象の各銘柄は信託報酬も低く設定されているものが多く、厳選されたETFが手数料無料で運用できることがauカブコム証券の強みです。
楽天証券 - 業界トップレベルのETF取扱数!
続いて紹介する証券会社が楽天証券です。楽天証券は海外ETFの取扱銘柄数が約364銘柄と業界トップの取扱数を誇っています。銘柄数が豊富な分、自分の投資スタイルにあった銘柄を見つけられる可能性が高くなります。取り扱い海外ETFの豊富さは楽天証券の大きな強みだといえます。

また手数料無料のETFの取扱数も103銘柄と、証券会社の中で1番の取扱数となっています。無料のETFを103銘柄の中から選べるので、手数料が無料かつ様々なスタイルの運用が可能になります。
しかし、銘柄選びで手数料と合わせて注意したいのが「信託報酬」です。手数料が無料な分、それぞれの銘柄の信託報酬を気に掛けるようにしないと手数料無料のメリットが薄れてしまいます。なので手数料が無料だからといって、信託報酬の吟味を怠らないよう気を付けましょう。
とはいえ、楽天証券もまた低コストでETFを運用でき、投資初心者にもオススメできる証券会社となっています。
マネックス証券 - 海外ETFなら大注目の「ゼロETF」
最後に紹介するのはマネックス証券です。マネックス証券の魅力は、330銘柄を超える海外ETFの取扱数と「ゼロETF」と呼ばれる手数料無料の海外ETFを扱っている点が挙げられます。
まず海外ETF取扱数ですが、楽天証券には劣るものの、330銘柄以上という業界でも屈指のETF取扱数を誇ります。そのため、マネックス証券においても自分の投資スタイルにあった銘柄を見つけられる可能性が高いと言えます。

続いて「ゼロETF」ですが、これは特定の米国ETFに限り手数料が実質無料になるというマネックス証券独自のサービスになります。
具体的にはマネックス証券が新規に取り扱いを始めた海外ETFに関しては、取り扱い開始から6ヶ月間手数料が実質無料になります。さらにウィズタムツリーという運用会社が運用しているウィズダムツリーETFに関しては、恒久的に実質無料になります。
※海外ETFの取引にはマネックス証券の証券取引総合口座の他に外国株取引口座の開設が必要になるので注意しましょう。
まとめ
今回は、ETFの特徴や種類からメリット、デメリットまで紹介してきました。ETFは紹介してきた通り、全投資家にとって魅力の詰まった金融商品になっています。まだ投資に踏み切れていないという方はETFをきっかけに、投資家デビューをしてみてはいかがでしょうか。
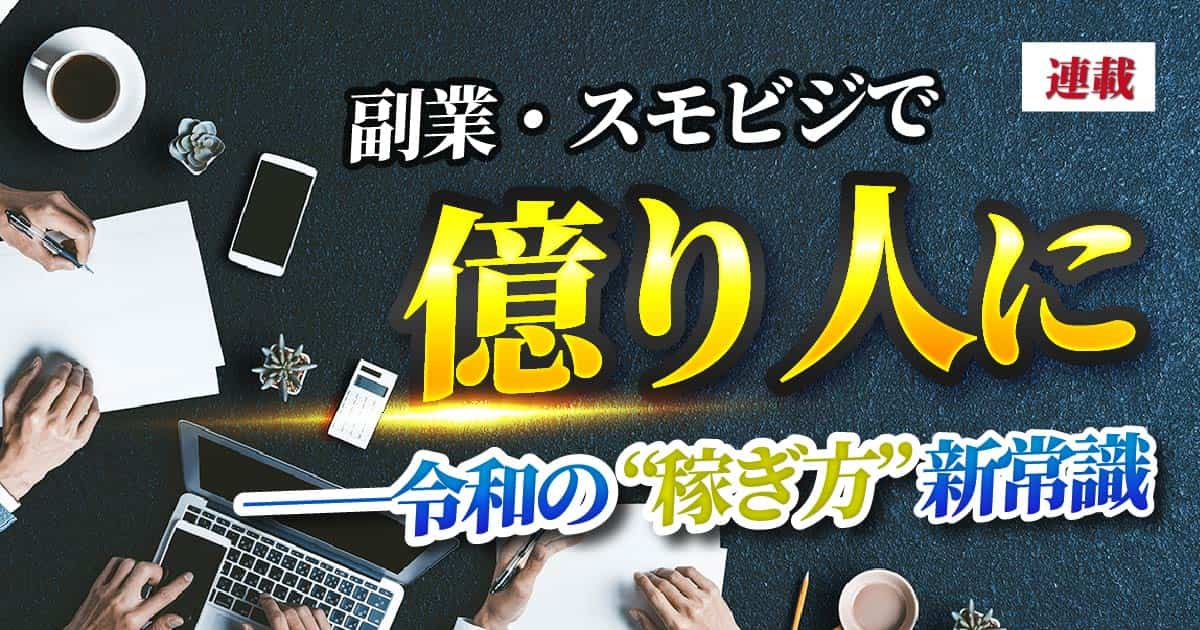




※noteで購入した記事はnote上でのみ閲覧可能です。
※プレミアム会員向けコンテンツと同一の内容を含みます。重複購入にご注意ください。